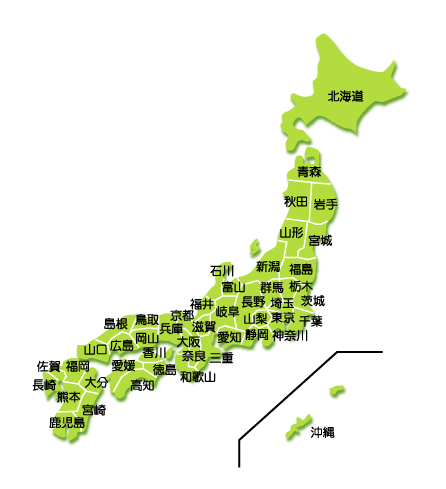| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国小野小町史跡一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↧
小野小町生誕地、終焉地多数
↧
奈良県何の日
これからどしどし追加して行きます、
609年8月8日=飛鳥大仏完成
621年12月21日=聖徳太子の母穴穂部間人皇女死去
622年2月22日=聖徳太子斑鳩宮で死去
671年10月19日=大海皇子吉野へ出発9-
698年10月14日=奈良に薬師寺完成
730年=興福寺五重塔建立
734年1月11日=興福寺西金堂建立
1089年2月5日=興福寺金堂焼失
1180年5月26日=頼政奈良に向かった?
1480年11月22日=興福寺十三重塔焼失
1495年11月22日=大和長谷寺炎上
1584年8月11日=大和順慶が大和郡山城で病死
1868年7月8日=奈良県設立
1950年5月18日=奈良競輪開場
1958年8月6日=生駒自動車道開通
1958年9月25日=藤の木古墳発掘
1964年9月20日=池原発電所送電開始(北山村)
1967年3月26日=葛城ロープウエイ開通
2009年3月20日=近鉄奈良ー阪神三宮直通運転開始
↧
↧
あけましておめでとう。2016
↧
2016年ウォーク思い出
1月2日=京都府ウォーキング協会
京都初詣ウォーク、14K。845名
1月3日=オレンジクラブ一歩会
京都五山ウォーク、15K
↧
2016年ウォーク思い出
1月2日=京都府ウォーキング協会
京都初詣ウォーク、14K。845名
1月3日=オレンジクラブ一歩会
京都五山ウォーク、15K
↧
↧
頭に触れるだけで痛し、眠れない
10月23に頃より
頭が触れるだけでズキンズキン痛みます。横になって寝ころぶと頭に触れるので痛い、洗髪も出来ないし、眠れない
頭がふわふわして重苦しい
何かいい知恵ありませんか。
退院しました。お見舞い訪問ありがとう。
10月5日無事に退院することが出来ました、これより1か月、2か月療養してウォークに参加できるように専念します。
交通事故で大変ご迷惑おかけしました。
これからもよろしく
腰以外は元気です。
9月14日ウォーキングに参加の為に
近鉄京都線桃山御陵駅を下車して
集合場所の桃山御陵入口にむかっていました。
JR奈良線桃山駅西側の午前9時頃、踏切を渡り交差点の青信号を確認をした、左右の車両はなかった、右折してくる車両は2台も確認して渡っていた時右折してきた、車両に
両手を衝いたまま後ろ向きに倒された。
腰が思い切り強打して立つことが出来ず
救急車で宇治徳洲会病院に搬送された。
uji健歩会皆さんに同乗していただき
大変ご迷惑おかけしました。
又皆さんといっしょうに1日でも早く歩けますように療養に専念します。
9月14日に加害者側訪問
保険会社より電話
9月18日に通院9時に病院へ
診察。レントゲンを受けた結果
骨盤右側の部分がヒビが入ってることが
わかりました。そしてコルセットの寸法
測る
9月19日に保険会社より電話、書類郵送されてくる、
9月21日に加害者訪問
9月24日=食事直後腹部左下が激痛。CT検査。レントゲン。造影剤CT検査その後入院
9月25日=午前4時小便出ずに激痛、に
管で11時までに2000cc出る
コルセット装着
9月26日=胃附近激痛に移る。
9月27日=浣腸、体重48、5K
9月28日=右側太ももに激痛移る
10月2日レントゲン、診察
まだ、骨盤にひびが、
加害者上司2名
10月3日=初めて病室内歩く
10月4日=看護師同行の上病院内歩く退院会議
10月5日=退院
体重47,2キロ、事故前は49,7K
10月12日=両足のしびれがきつく
夜あまり眠れないように
10月14日=妻が入院
10月15日=妻が白内障手術
10月17日=妻が退院
10月23日~26日あまり眠れない続く
10月27日=左側の頭部、首、肩がズキンズキンと痛くなり病院へ片頭痛
CT検査受けるが異常なし
10月30日=片頭痛の薬飲んでも効かないので脳神経科へ原因不明と言われ
カローナル飲むが効かない。
11月4日にMRI検査
整形外科レントゲンよくなりコルセット外しオッケ
11月に入っても頭が痛くて眠れない。
11月4日=MRI検査
妻は眼科へ
11月6日=脳神経科診察MRIは異常なし
痛みの原因不明。相変わらず痛みは続く
11月13日=宇治徳洲会病院へ紹介で
宇治武田病院へ(痛みは続く)
後頭神経痛と病名着けられる
11月20日=妻、心臓血管内科予約
11月27日=整形外科レントゲン、診察
予約
12月4日=朝から頭重く吐き気悠痛
病院へ37,8度風邪ひき
↧
奈良初詣ウォーク
2016年1月11日、大阪ウォーキング連合
奈良初詣。13K
JR奈良駅
興福寺三重塔、毎年7月7日特別公開
興福寺北円堂
興福寺南円堂
興福寺五重塔
氷室神社
東大寺大仏殿
東大寺二月堂
東大寺三月堂
東大寺四月堂
手向山神社
春日大社
若宮神社
東山緑地
新薬師寺
志賀直栽旧居
頭塔
元興寺塔跡
庚申堂
御霊神社
元興寺極楽坊
ならまち
恵比寿神社
率川神社
JR奈良
↧
日本の戦争何の日年表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
↧
長野県スキーバス転落14人死亡
ニュース詳細
スキーバス転落で14人死亡 バス会社を捜索へ1月15日11時27分

k10010372281_201601151228_201601151233.mp4
15日午前2時ごろ、長野県軽井沢町のバイパスでスキー客を乗せたバスが道路から転落し、警察によりますと、バスに乗っていた41人のうち乗客12人と乗員2人の合わせて14人の死亡が確認されました。このほか27人が病院に搬送されて手当てを受けていて、この中には意識がない人もいるということです。警察は過失運転致死傷の疑いで東京のバス運行会社を捜索する方針です。
15日午前2時ごろ、長野県軽井沢町の国道18号の碓氷バイパスで、スキーツアー客を乗せて群馬方面から長野方面に向かっていたバスが、反対車線に出てガードレールを乗り越え、道路の下に転落しました。
このバスには乗客39人と乗員2人の合わせて41人が乗っていて、警察によりますと、乗客12人と運転手ら乗員2人の合わせて14人の死亡が確認されました。14人のうち9人が男性で、5人が女性だということです。また、27人が病院に搬送されて手当てを受けていて、病院によりますと、この中には意識がない人もいるということです。乗客の多くは10代や20代の若い人だということです。
このスキーツアーを企画した東京・渋谷区の「キースツアー」によりますと、このバスは14日夜、東京を出発して、長野県飯山市の斑尾高原に向かっていたということです。
現場は入山峠から長野県方面に1キロほど下ったところで、上りが2車線、下りが1車線になっています。バスは下りの車線を走行していて、反対車線のガードレールを乗り越えて、およそ3メートル下に転落したということです。車体は道路下の木に当たった状態で横転していて、天井部分などが大きくえぐられるようにへこみ、めちゃめちゃに壊れています。
道路を管理する高崎河川国道事務所によりますと、碓氷バイパスのおよそ16キロの区間には合わせて45か所のカーブがあり、事故が起きたのは群馬県側から数えて43か所目のカーブだったということです。現場のカーブはゆるやかで、当時、路面は凍結などはしていませんでした。
警察は東京・羽村市のバス運行会社の関係者から事情を聞いているほか、過失運転致死傷の疑いで会社を捜索する方針で、事故が起きた原因について調べを進めることにしています。
このバスには乗客39人と乗員2人の合わせて41人が乗っていて、警察によりますと、乗客12人と運転手ら乗員2人の合わせて14人の死亡が確認されました。14人のうち9人が男性で、5人が女性だということです。また、27人が病院に搬送されて手当てを受けていて、病院によりますと、この中には意識がない人もいるということです。乗客の多くは10代や20代の若い人だということです。
このスキーツアーを企画した東京・渋谷区の「キースツアー」によりますと、このバスは14日夜、東京を出発して、長野県飯山市の斑尾高原に向かっていたということです。
現場は入山峠から長野県方面に1キロほど下ったところで、上りが2車線、下りが1車線になっています。バスは下りの車線を走行していて、反対車線のガードレールを乗り越えて、およそ3メートル下に転落したということです。車体は道路下の木に当たった状態で横転していて、天井部分などが大きくえぐられるようにへこみ、めちゃめちゃに壊れています。
道路を管理する高崎河川国道事務所によりますと、碓氷バイパスのおよそ16キロの区間には合わせて45か所のカーブがあり、事故が起きたのは群馬県側から数えて43か所目のカーブだったということです。現場のカーブはゆるやかで、当時、路面は凍結などはしていませんでした。
警察は東京・羽村市のバス運行会社の関係者から事情を聞いているほか、過失運転致死傷の疑いで会社を捜索する方針で、事故が起きた原因について調べを進めることにしています。
関連ニュース[自動検索]
↧
↧
東宇治史跡、寺院探訪ウォーク
2016年1月17日、宇治市歩こう会。8K、参加者76名
東宇治史跡探訪ウォーク
宇治公民館
例会に50回、100回、150回参加者に宇治市長賞
厳島神社=
宇治市菟道の静かな住宅街の中にある厳島神社。777年降雨祈願のため広島の厳島神社と同じ
市杵嶋比売命(イチキシマヒメノミコト)を歓請し、社殿を建てたと考えられています。
市杵嶋比売命(イチキシマヒメノミコト)を歓請し、社殿を建てたと考えられています。
安養寺=
安養寺は都の辰巳、即ち京都市から南西方向、宇治市に位置します。西院よりの駅は京阪電車の三室戸駅・JR宇治駅で、黄壁山万福寺と平等院の中間辺りに位置します。寺の前を通る道路は旧奈良街道と呼ばれ、その昔京都の都から奈良の都を結び牛車が通ったと云われる古い街道です。寺は主にこの地域に住む茶師の帰依を受け繁栄し現在に至っています。元は天台宗で、天文7年(1538)に増念誉助心が再興してから浄土宗に改められ、現在地に移転したのは貞享2年(1685)と云われています。
蔵林寺=986年恵心僧都開創したが荒廃したため
1470年再興された。
地蔵菩薩立像、毘沙門天立像。薬師如来坐像などある。ここにあるむくの木は樹齢500年
隼上り瓦窯跡=1982年宅地造成中に4基発見
1986年6月9日国指定史跡に
蘇我氏の氏寺豊浦寺に供給
許波多神社鳥居柱=五ヶ庄の旧社の鳥居の柱
許波多神社跡=現代五ヶ庄許波多神社の旧地
黄檗公園、昼食
萬福寺=
黄檗宗は、中国・明時代の高僧隠元隆禅師が1654年に日本に来られ、伝え、広めた禅宗の一派です。臨済宗の流れをくんでいるのですが、四代将軍家綱より許可を得て、宇治に黄檗山萬福寺を開くことにより、正式に黄檗宗が認められたのです。
![]() 萬福寺は中国明朝の伽藍様式を取り入れて、他の宗派にはない中国風な香りを感じることができる寺院です。
萬福寺は中国明朝の伽藍様式を取り入れて、他の宗派にはない中国風な香りを感じることができる寺院です。
総門の屋根の上には摩伽羅(まから)という像があります。摩伽羅とはガンジス河の女神の乗り物で、そこに生息しているワニをさす言葉です。アジアでは、聖域結界となる入り口の門・屋根・仏像等の装飾に使われています。
 萬福寺は中国明朝の伽藍様式を取り入れて、他の宗派にはない中国風な香りを感じることができる寺院です。
萬福寺は中国明朝の伽藍様式を取り入れて、他の宗派にはない中国風な香りを感じることができる寺院です。総門の屋根の上には摩伽羅(まから)という像があります。摩伽羅とはガンジス河の女神の乗り物で、そこに生息しているワニをさす言葉です。アジアでは、聖域結界となる入り口の門・屋根・仏像等の装飾に使われています。
宇治村道路元標=
宇治市内に宇治橋西詰に宇治町、槙島堤に槙島村の
道路元標がある
許波多神社(五ヶ庄)=明治9年宇治火薬庫用地になった為旧御旅所に移築、本殿は重文
寺界道遺跡=
藤原氏えい域、宇治陵1号墳=
西導寺=
広芝の地にあった二階堂という庵室を、慶長10年 (1605) 円誉(えんよ)上人が寺として再興。享保10年 (1730) に現在の地に移った。付近の廃寺から伝えられたとされる多くの仏像がある。毘沙門天像も、もとは五ヶ庄地域の南端に営まれた畑寺にあり、明治初年にそれが廃寺となり、本寺に移安されたと伝えられる。平安時代後期の作で、桧材一木造り・像高103.0cm。
両足・岩座部分が本体と一体で、底部が削り取られていて安定性を著しく欠く。幾度も転倒し、上体部剥ぎ目が離れ、現在は横にして保管していたため、剥ぎ目を強固に接合の上、像の立ちの安定を図る修理に対して助成を行った。(平成17年度)
両足・岩座部分が本体と一体で、底部が削り取られていて安定性を著しく欠く。幾度も転倒し、上体部剥ぎ目が離れ、現在は横にして保管していたため、剥ぎ目を強固に接合の上、像の立ちの安定を図る修理に対して助成を行った。(平成17年度)
二子塚古墳=1914年京阪宇治線建設により後円部
破壊され、その後発掘、調査、1995年公園に
前方後円墳、6世紀初期築造
能化院=坂上田村麻呂が桓武天皇の勅願により建立
802年延鎮自作の八尺の千手観世音安置
998年恵心僧都再建、地蔵菩薩像(重文)自作
1159年、1221年に焼失したが地蔵菩薩は難を逃れた。常盤御殿の腰かけ残る
JR木幡=奈良鉄道1896年1月25日開業
1905年2月奈良鉄道は関西鉄道に吸収される。
1907年関西鉄道国有化に
↧
近畿地方の城郭
近畿地方の城郭
河内・丹南陣屋 |  |
 写真館(14枚) 写真館(14枚)
|
↧
京都通りの歌
京都市通りの歌
南北の通り(寺御幸)
| てらごこふやとみ やなぎさかい たかあいひがし くるまやちょう からすりょうがえ むろころも しんまちかまんざ にしおがわ あぶらさめがいで ほりかわのみず よしやいのくろ おおみやへ まつひぐらしに ちえこういん じょうふくせんぼん はてはにしじん |
| 寺御幸麩屋富柳堺 高間東車屋町 烏両替室衣 新町釜座西小川 油醒ヶ井で堀川の水 葭屋猪黒大宮へ 松日暮に智恵光院 浄福千本果ては西陣 |
寺町、御幸町、麩屋町、富小路、柳馬場、堺町、高倉、間之町、東洞院、車屋町、烏丸、両替町、室町、衣棚、新町、釜座、西洞院、小川、油小路、醒ヶ井、堀川、葭屋町、猪熊、黒門、大宮、松屋町、日暮、智恵光院、浄福寺、千本
「西陣」は通りの名ではない。
東西の通り(丸竹夷)
| まるたけえびすに おしおいけ あねさんろっかく たこにしき しあやぶったか まつまんごじょう せったちゃらちゃら うおのたな ろくじょうさんてつ とおりすぎ ひっちょうこえれば はっくじょう じゅうじょうとうじで とどめさす |
| 丸竹夷二押御池 姉三六角蛸錦 四綾仏高松万五条 雪駄ちゃらちゃら魚の棚 六条三哲通りすぎ 七条越えれば八九条 十条東寺でとどめさす |
丸太町、竹屋町、夷川、二条、押小路、御池、姉小路、三条、六角、蛸薬師、錦小路、四条、綾小路、仏光寺、高辻、松原、万寿寺、五条、 (雪駄屋町)、鍵屋町、(銭屋町)、(魚棚)、六条、三哲、七条、八条、九条、十条、東寺
下を「五条」で唄を終えることもある。また、魚の棚以南の個所には異なって伝わっている歌詞が多くある。比較的よく歌い慣らされているのは、上記の通り、十条通を歌い込むものだが、三哲通(塩小路通)が七条通より早く歌われるとともに、九条通にある東寺を十条通とともに掲げるなど、実際の通りの順序と異なって歌われている。さらに十条通は昭和期に作られた新しい通りであることなどから、語呂合わせを混ぜながら時代により変化していたとも考えられている。
なお、上は丸太町通から始まっているが、江戸時の町家の上手は概ね丸太町から始まり、下は五条程度であった。また、昭和初期まではその外では田畑も多かった。このため終わりが七条までになっている歌詞もある(下表参照)。
| せったちゃらちゃら うおのたな じゅずやふたすじ まんねんじ ひっちょうこえて とおりみちなし |
| 雪駄ちゃらちゃら魚の棚 珠数屋二筋万年寺 七条越えて通り道なし |
また、通りを歌う順番を実際の並びの通りに示した歌詞もある(下表参照)。
| せったちゃらちゃら うおのたな ひっちょう さんてつ とおりすぎ はっちょうこえれば とうじみち くじょうおおじで とどめさす |
| 雪駄ちゃらちゃら魚の棚 七条三哲通りすぎ 八条越えれば東寺道 九条大路でとどめさす |
また、丸竹夷の最初につけて丸太町通から北の東西通り名を歌いこむ歌詞として、以下のものがある。
| くらやてら かみだちいつつ いまやもと むいちなかだち ちょうじゃみとおり でみずしも さわらぎ… |
| 鞍や寺 上立五つ 今や元 武一中立 長者三通り 出水下 椹木… |
鞍馬口、寺之内、上立売、五辻、今出川、元誓願寺、武者小路、一条、中立売、上・中・下長者町、出水、下立売、椹木町
また、丸竹夷も、寺御幸についても、上に掲げるもの以外のバリエーションは数多く存在する。また、丸竹夷(東西の通り)に続いて、寺御幸(南北の通り)を歌うものもある。
寺御幸
- 「浄福千本さては西陣」(じょうふくせんぼんさてはにしじん)
丸竹夷
- 「九条十条でとどめさす」(くじょうとうじょで とどめさす)
その他
その他有名なものとして、丸太町通から松原通までの東西の通りを歌うものとして以下のものがある。
| ぼんさんあたまはまるたまち つるっとすべってたけやまち みずのながれはえびすがわ にじょうでこうたきぐすりを ただでやるのはおしこうじ おいけでおうた(でおうた)あねさんに ろくせんもろうてたここうて にしきでおとしてしかられて あやまったけどぶつぶつと たかがしれた(て・と)るまどしたろ |
| 丸太町通 竹屋町通 夷川通 二条通 押小路通 御池通 姉小路通 三条通 六角通 蛸薬師通 錦小路通 四条通 綾小路通 仏光寺通 高辻通 松原通 |
↧
大相撲元横綱琴桜の孫序の口優勝
元横綱琴桜(祖父)、元関脇琴の若(父)
琴桜の孫琴鎌谷が序の口優勝

<div class="alertBox">< div class="alert">< i></i><p>現在<em>JavaScriptが無効</em>になっています。Yahoo!ニュースのすべての機能を利用するためには、JavaScriptの設定を有効にしてください。
佐渡ケ嶽親方(元関脇琴ノ若)の長男、琴鎌谷(佐渡ケ嶽部屋)が7戦全勝で序ノ口優勝を果たした。この日も大きな体を生かして前に出る内容で「優勝のことを考えずに自分の相撲を取ろうと思った」と落ち着いた口調で語った。「勝ち負けより自分の相撲を取り切ることを考えたい。まずは関取を目標に」。元横綱の琴桜を祖父に持つ大器は、浮かれるそぶりも見せなかった。
↧
↧
己の縁起、神社。寺院
上神明天祖神社
東京都品川区
大豊神社
京都市左京区鹿が谷
磯山弁財天
栃木県佐野市出流原町
久下田白蛇弁財天
栃木県
白蛇神社
山口県岩国市今津町
阿蘇白蛇神社
熊本県南阿蘇村
高天ヶ原神社
埼玉県川越市
大谷観音
栃木県宇都宮市
三室戸寺
京都府宇治市菟道
珍しい狛犬
神々しい「蘇羅比古神社」と、空を見つめる狛犬
広島県庄原市本村にある「蘇羅比古神社」へ行きました。
平安時代に作られた「延喜式神名帳」の記載では「蘇羅比古神社」は、備後国三上郡の小社で、祭神は、天津日高日子穗穗手見命(あまつひこひこほほでみ)、神倭伊波禮毘古命(かむやまといはれびこのみこと)」とあります
平安時代に作られた「延喜式神名帳」の記載では「蘇羅比古神社」は、備後国三上郡の小社で、祭神は、天津日高日子穗穗手見命(あまつひこひこほほでみ)、神倭伊波禮毘古命(かむやまといはれびこのみこと)」とあります
www.geocities.jp/shibakin2002/hanazono-2.html - キャッシュ。クリックしてください。
石楠花に包まれる「拝殿」, 茨城百景・観光百選 「花園神社」, 花園神社の境内(05/05/ 05). 鎮座地:北茨城市華川町花園567 mapion ... 花園神社の創立は、約1200年前の 昔、延暦14乙亥年年(795年)、征夷大将軍「坂上田村磨」が奥州下向の折に、草創され たといわれて ... 御本殿の前の狛犬(右側) ... 北茨城市商工会 茨城県林業技術センター
常堅寺までは、駐車場から長閑な畑の小道を数分歩きます。 寺院の裏手の小川が、『遠野物語』で有名なカッパ淵です。 境内には河童に因んだ石碑や、カッパ狛犬もいます。 カッパで有名ではありますが、常堅寺自体も室町時代の1490年に創建された由緒ある寺院で、特に山門と阿吽像は重厚な歴史を感じさせます。
↧
戦災で焼失した国宝
原爆被害
日本本土への艦砲射撃民間船舶の被害
鉄道車両への機銃掃射
- 広島市への原子爆弾投下(1945年8月6日)
- 長崎市への原子爆弾投下(1945年8月9日)
その他の被害[編集]
- 国宝、重要文化財、史跡等建築物の被害
- http://www.city.okayama.jp/hofuku/engo/engo_00010.html
- 岡山県の戦災で焼けた施設
↧
甘利経済再生担当相辞任表明
2016年1月28日(木) 17時42分掲載
甘利経済再生担当相が辞任表明
甘利明経済再生担当相(66)=衆院神奈川13区=は28日夕、内閣府で記者会見し、週刊文春が報じた金銭授受疑惑の責任を取って辞任すると表明した。甘利氏はこれに先立ち、安倍晋三首相に辞意を伝えた。首相は平成28年度予算案など重要法案の審議や今夏の参院選に影響を与えかねないと判断した。野党は首相の任命責任への追及を強める構えだ。(産経新聞)
[記事全文]「生き様に反する」
- <甘利明経済再生担当相>「生き様に反する」閣僚辞任を表明
- 毎日新聞(2016年1月28日)
2回の現金授受認める
- 甘利大臣 2回の現金授受認める 大臣室と事務所で
- NHK(2016年1月28日)
- 100万円の受領認める=甘利氏
- 時事通信(2016年1月28日)
会見の中継サイト
- 【ライブ中継】金銭授受疑惑で甘利明経済再生担当相が会見中
- THE PAGE(2016年1月28日)
週刊文春が報じた疑惑
- 衝撃告発「私は甘利大臣に賄賂を渡した!」
- 週刊文春(2016年1月20日)
- 金銭授受疑惑 甘利大臣秘書の“UR威圧録音”入手!
- 週刊文春(2016年1月27日)
辞任をどう思う?
- 甘利経済再生相の辞任は妥当?
- 意識調査
関連トピックス
【甘利氏辞任】「恥ずかしい事実が判明した」![写真あり]() 小山田氏が頭取昇格 三菱東京UFJ銀行
小山田氏が頭取昇格 三菱東京UFJ銀行![写真あり]() 【甘利氏辞任】「秘書に責任転嫁することはできない」
【甘利氏辞任】「秘書に責任転嫁することはできない」![写真あり]() 【甘利氏疑惑】甘利経済再生担当相が辞任表明
【甘利氏疑惑】甘利経済再生担当相が辞任表明![写真あり]() 著名中国紙編集長を処分 人民日報系、経費で旅行【甘利氏疑惑】国交省が甘利氏会見前の報告を拒否 民主・維新追及チームが「意図的な調整だ」
著名中国紙編集長を処分 人民日報系、経費で旅行【甘利氏疑惑】国交省が甘利氏会見前の報告を拒否 民主・維新追及チームが「意図的な調整だ」![写真あり]()
甘利氏辞任 経済再生相後任に自民党の石原伸晃元幹事長
安倍晋三首相は28日、辞任を表明した甘利明経済再生担当相の後任に、自民党の石原伸晃元幹事長を起用する意向を固めた。(産経新聞)
後任に
↧
平安貴族の雅と新緑ウォーク2014年5月22日
平安貴族の雅と新緑ウォーク2014年5月22日。12K
京都府ウォーキング協会
JR奈良線宇治駅=
1896年(明治29年)1月25日 - 奈良鉄道の桃山駅 - 玉水駅間延伸時に開業。
1905年(明治38年)2月7日 - 合併により関西鉄道の駅となる。
1907年(明治40年)10月1日 - 関西鉄道が国有化。国鉄の駅となる。
1984年(昭和59年)2月1日 - 貨物列車の設定廃止。
- 駅南側にあるユニチカ宇治工場に向けて専用線が分岐し、タンク車による化学薬品の輸送が行われていた。
夢浮橋=
薫君(かおるのきみ)は、小野の里にいるのが、浮舟であることを聞き、涙にくれる。そして僧都にそこへの案内を頼んだ。僧都は、今は出家の身である浮舟の立場を思い、佛罰を恐れて受け入れなかったが、薫君が道心(どうしん)厚い人柄であることを思い、浮舟に消息を書いた。
薫君は浮舟の弟の小君(こぎみ)に、自分の文(ふみ)も添えて持って行かせた。
浮舟は、なつかしい弟の姿を覗き見て、肉親の情をかきたてられ母を思うが、心強く、会おうともせず、薫君の文も受け取らなかった。
小君は姉の非情を恨みながら、仕方なく京へ帰って行った。薫君はかつての自分と同じように、誰かが浮舟をあそこへかくまっているのではないかとも、疑うのだったとか。
薫君は浮舟の弟の小君(こぎみ)に、自分の文(ふみ)も添えて持って行かせた。
浮舟は、なつかしい弟の姿を覗き見て、肉親の情をかきたてられ母を思うが、心強く、会おうともせず、薫君の文も受け取らなかった。
小君は姉の非情を恨みながら、仕方なく京へ帰って行った。薫君はかつての自分と同じように、誰かが浮舟をあそこへかくまっているのではないかとも、疑うのだったとか。
世界遺産平等院=
平等院の創建[編集]

浄土式庭園と鳳凰堂
京都南郊の宇治の地は、『源氏物語』の「宇治十帖」の舞台であり、平安時代初期から貴族の別荘が営まれていた。現在の平等院の地は、9世紀末頃、光源氏のモデルともいわれる左大臣で嵯峨源氏の源融が営んだ別荘だったものが宇多天皇に渡り、天皇の孫である源重信を経て長徳4年(998年)、摂政藤原道長の別荘「宇治殿」となったものである。道長は万寿4年(1027年)に没し、その子の関白・藤原頼通は永承7年(1052年)、宇治殿を寺院に改めた。これが平等院の始まりである。開山(初代執印)は小野道風の孫にあたり、園城寺長吏を務めた明尊である。創建時の本堂は、鳳凰堂の北方、宇治川の岸辺近くにあり大日如来を本尊としていた。翌天喜元年(1053年)には、西方極楽浄土をこの世に出現させたような阿弥陀堂(現・鳳凰堂)が建立された。
塔の島=

十三重の塔(重文)
宇治神社=
菟道稚郎子命(うじのわきいらつこのみこと)
早蕨=
年改まり、宇治の山荘にも春が来た。
今年も山の阿闇梨(あざり)から蕨や土筆(つくし)などが贈られてきた。
中君(なかのきみ)は亡き父君や姉君を偲びつつ
この春はたれにか見せむ亡き人の
かたみにつめる峰の早蕨
と返歌なさった。
二月の上旬、中君は匂宮(におうのみや)の二条院へ迎えられ、行先の不安を感じつつも、幸福な日々が続く。
夕霧左大臣は、娘の六君(ろくのきみ)を匂宮にと思っていたので、失望し、薫君(かおるのきみ)にと、内意を伝えたが、大君(おおいきみ)の面影を追う薫君は、おだやかに辞退した。
花の頃、宇治を思いやる薫君は、二条院に、中君を訪ねては懇ろに語るが、匂宮は二人の仲を、疑い始める。
年改まり、宇治の山荘にも春が来た。
今年も山の阿闇梨(あざり)から蕨や土筆(つくし)などが贈られてきた。
中君(なかのきみ)は亡き父君や姉君を偲びつつ
この春はたれにか見せむ亡き人の
かたみにつめる峰の早蕨
と返歌なさった。
二月の上旬、中君は匂宮(におうのみや)の二条院へ迎えられ、行先の不安を感じつつも、幸福な日々が続く。
夕霧左大臣は、娘の六君(ろくのきみ)を匂宮にと思っていたので、失望し、薫君(かおるのきみ)にと、内意を伝えたが、大君(おおいきみ)の面影を追う薫君は、おだやかに辞退した。
花の頃、宇治を思いやる薫君は、二条院に、中君を訪ねては懇ろに語るが、匂宮は二人の仲を、疑い始める。
世界遺産宇治上神社=
中央の内殿、「中殿」は応神天皇を、「左殿」(向かって右側)は菟道稚郎子(うじのわきいらつこ:応神天皇の末の皇子)を、「右殿」(向かって左側)は仁徳天皇(応神天皇の皇子)を祀っている。
左の写真は中央の内殿「中殿」である。
左の写真は中央の内殿「中殿」である。
総角=
八宮(はちのみや)の一周忌がめぐって来た。薫君(かおるのきみ)は仏前の名香(みょうごう)の飾りに託して、大君(おおいきみ)への想いを詠んだ。
総角に長き契りを結びこめ
おなじ所によりもあはなむ
大君は父君の教えに従い、自らは宇治の山住みで果てる意思が堅く、妹の中君(なかのきみ)をこそ薫君に委ねたいと望まれた。
薫君は中君と匂宮(におうのみや)とが結ばれることによって、大君の心を得ようとされたが、意外な結果に事が運ばれてしまう。
匂宮は中君と結ばれたが、気儘に行動され得ない御身分故、心ならずも宇治への訪れが遠のく。大君は「亡き人の御諌めはかかる事にこそ」と故宮をしのばれ、悲しみのあまり、病の床につき、薫君の手あつい看護のもとに、冬、十一月に、薫君の胸に永遠の面影を残して、帰らぬ人となった。
総角に長き契りを結びこめ
おなじ所によりもあはなむ
大君は父君の教えに従い、自らは宇治の山住みで果てる意思が堅く、妹の中君(なかのきみ)をこそ薫君に委ねたいと望まれた。
薫君は中君と匂宮(におうのみや)とが結ばれることによって、大君の心を得ようとされたが、意外な結果に事が運ばれてしまう。
匂宮は中君と結ばれたが、気儘に行動され得ない御身分故、心ならずも宇治への訪れが遠のく。大君は「亡き人の御諌めはかかる事にこそ」と故宮をしのばれ、悲しみのあまり、病の床につき、薫君の手あつい看護のもとに、冬、十一月に、薫君の胸に永遠の面影を残して、帰らぬ人となった。
源氏物語ミュージアム
蜻蛉=
宇治の山荘は、浮舟(うきふね)の失踪で大騒ぎとなった。事情をよく知る女房達は、入水を推察して、世間体を繕うため母を説得し、遺骸の無いまま泣く泣く葬儀を行った。薫君(かおるのきみ)も匂宮(におうのみや)も悲嘆の涙にくれたが、思いはそれぞれ違っていた。
事情を知った薫君は、自らの恋の不運を嘆きながらも、手厚く四十九日の法要を営んだ。
六条院では、明石中宮(あかしのちゅうぐう)が光源氏や紫上(むらさきのうえ)のために法華八講(ほっけはっこう)を催された。都では、華やかな日々を送りながらも薫君は、大君(おおいきみ)や浮舟との「つらかりける契りども」を思い続けて愁いに沈んでいた。
ある秋の夕暮、薫君は、蜻蛉がはかなげに飛び交うのを見て、ひとり言を口ずさむのだった。
事情を知った薫君は、自らの恋の不運を嘆きながらも、手厚く四十九日の法要を営んだ。
六条院では、明石中宮(あかしのちゅうぐう)が光源氏や紫上(むらさきのうえ)のために法華八講(ほっけはっこう)を催された。都では、華やかな日々を送りながらも薫君は、大君(おおいきみ)や浮舟との「つらかりける契りども」を思い続けて愁いに沈んでいた。
ある秋の夕暮、薫君は、蜻蛉がはかなげに飛び交うのを見て、ひとり言を口ずさむのだった。
隼上り瓦窯跡=
京都府宇治市莵道(うどう)にある窯跡。京都府南部、宇治川中流にある宇治橋の北東約1.5kmに位置し、東から西に延びる丘陵の南斜面に所在。4基の窯跡、工房跡、灰原などが検出されたが、出土した軒丸瓦(のきまるがわら)の多くは奈良県高市郡明日香村にある豊浦(とゆら)寺跡から出土した瓦と同笵(どうはん)であり、50kmも離れた寺院に供給されていたことが判明した
黄檗公園、=昼食
周辺軍事工場跡、火薬工場跡、許波多神社跡碑
陸軍省用地碑などある
黄檗トンネル、長さ620m=
接続道路
- 京都府道3号大津南郷宇治線(宇治川ライン)
- 宇治市道黄檗山手線(黄檗トンネル)
- 京都府道7号京都宇治線(宇治街道)
平尾台児童公園
日野誕生院=
本願寺第十九代宗主本如上人は、文化年間(1804~1818年)に日野氏の由緒地を調査し、親鸞の父である日野有範(ありのり)公に因み「有範堂」を建立した。その後、第二十一代宗主明如上人の時代に本願寺の飛地境内地として「日野別堂誕生院」と改称した。また境内地西側には親鸞誕生の際に使用されたと伝わる「産湯の井戸」と親鸞のへその緒を納めた「胞衣(えな)塚」がある
日野法界寺=
平安時代後期の永承6年(1051年)、もと文章博士で後に出家した日野資業が、薬師如来を安置する堂を建てたのが法界寺の始まりとされている。薬師如来像の胎内には、日野家に代々伝わる、伝教大師最澄自作の三寸の薬師像を納入したという。
日野児童公園、トイレ
醍醐中学校
一言寺=
もとは藤原通憲(信西)の娘で建礼門院に仕えた阿波内侍の開基により創建されたと伝えられ、この寺の南側からは1973年(昭和48年)の発掘調査により、鎌倉時代の庭園跡などが発見されている。創建されて以後寺は次第に衰退したが、1874年(明治8年)醍醐寺の塔頭である金剛王院が移されて復興された。
黒門=
醍醐寺の黒門付近で、塀の塗替え作業に思わず立ち止まってしまいました。伝統文化の継承に携わっていらっしゃる方に敬意を払います
醍醐寺三宝院=
874年(貞観16年)、空海の孫弟子にあたる理源大師聖宝が笠取山に醍醐寺を創建した。山頂付近は「上醍醐」、山麓一帯は「下醍醐」と呼ばれ、堂塔伽藍が立ち並び繁栄した。三宝院は1115年(永久3年)、醍醐寺第14代座主勝覚が開いたもので、歴代の座主を輩出し、1428年(応永35年)以降は三宝院主が醍醐寺座主の地位を独占した。しかし醍醐寺は1467年(応仁元年)に始まった応仁の乱の兵火に巻き込まれ、三宝院を含む多くの建物が焼失し、一帯は荒廃してしまう。
京都市営地下鉄醍醐駅
↧
↧
真田幸村生涯年表
- 真田幸村の生涯が簡単にわかる年表
真田幸村の生涯が簡単にわかる年表
波瀾万丈の生涯を遂げた真田幸村こと真田信繁、巷間伝わる逸話の中には後世に軍談物や講釈によって脚色された真田十勇士を率いての活躍など、伝説的なものも多いのですが、ここでは確認できる史料を中心にした年譜を簡単にご紹介していきます。
真田幸村の生涯
永禄10年(1567年)
真田幸村誕生。 父は真田昌幸、母は正室山手殿。兄に真田信之。
昌幸は当時、武田信玄の母方の大井氏の支族である武藤家の養子となり、武藤喜兵衛昌幸を名乗っていました。身分は騎馬15騎、足軽30人を率いる足軽大将であったと伝えられています。
このころの真田家は信濃国小県群国衆で、幸村の祖父にあたる幸綱が一族を統括し、武田信玄の重臣となっていました。
天正3年(1575年)
長篠の戦いにおいて父・昌幸の長兄信綱、次兄昌輝が戦死したため、昌幸は真田家当主となり、幸村も甲府を離れ、城代を務める上野国岩櫃城へ移ります。
天正10年(1582年)
3月11日 織田・徳川連合軍の侵攻によって武田勝頼が一族とともに自決し、武田家は滅亡すると、昌幸は信長に恭順し、上野国吾妻郡・利根郡、信濃国小県郡の所領を安堵されます。
6月 本能寺の変により信長が横死すると、越後の上杉、相模の北条、三河の徳川の間に武田遺領巡る天正壬午の乱が起こり、真田氏も武田の遺臣と遺領を取り込むべく画策します。
天正13年(1585年)
7月15日 武田旧領を巡る混戦の中で上杉、北条、上杉と同盟相手を次々に替えていた昌幸は、最終的に上杉景勝に臣従し、幸村は人質として上杉家に送られます。
幸村は徳川家との第一次上田合戦に出陣し、徳川に属した屋代氏の旧領が与えられています。
小牧・長久手の戦いを経て天下の形成が豊臣秀吉に傾くと、上杉氏は豊臣家を盟主と仰ぎ、人質であった幸村も大坂に送られたため真田家は豊臣氏に臣従することとなります。
天正18年(1590年)
3月 幸村は父・昌幸、兄・信幸とともに小田原北条氏攻略戦参加、真田家は石田三成の指揮下に入り、大谷吉継らと忍城攻めに加わります。
4月 昌幸は上野国松井田城攻めを命じられます。 この松井田城攻略戦が幸村の初陣となりました。
天正19年(1591年)
6月 陸奥では葛西大崎一揆、九戸政実の叛乱が起こったため、北条氏を滅ぼした豊臣秀吉は、引き続いて奥州征伐を実行します。 幸村も、昌幸、信之と共にこれに加わっています。
文禄元年(1592年)
2月 真田家は朝鮮の役に出陣を命じられ、幸村も父、兄と共に肥前名護屋に赴きます。 名護屋での真田家の役目は後備であったらしく朝鮮へは渡海していません。
文禄3年(1594年)
11月2日 幸村は従五位下左衛門佐に叙任されるとともに、豊臣姓を下賜されます。 またこのころ、豊臣家の重臣である大谷吉継の娘・竹林院を正室に迎えています。
Sponsored Links
慶長5年(1600年)
7月 豊臣秀吉没後、大坂城に入った徳川家康は、会津の上杉征伐を敢行。 幸村は父、兄とともに関東に向かいます。
同月、豊臣五奉行から、家康討つべしとの連署状が出され、下野犬伏の真田家の陣に石田三成の密使が到着します。
ここで、昌幸、信之、幸村は今後の去就を話し合い、徳川重臣・本多忠勝の婿であった信之はこのまま徳川方に、幸村と昌幸は大坂方に就くことを決して別れます。
ここで、昌幸、信之、幸村は今後の去就を話し合い、徳川重臣・本多忠勝の婿であった信之はこのまま徳川方に、幸村と昌幸は大坂方に就くことを決して別れます。
9月6日 幸村は昌幸と共に信州上田城に籠り、中山道制圧を目的とした徳川秀忠の大軍を相手に奮戦し、ついに秀忠軍が関ヶ原の合戦に参戦するのを妨げるという軍功を挙げます。
12月12日 9月15日に行われた関ヶ原合戦で西軍が敗北すると、幸村と昌幸は敗軍の将となりますが、信之とその舅の本多忠勝の助力もあって死をまぬがれ、紀伊国高野山麓の九度山に配流されます。
慶長17年(1612年)
九度山幽閉中の幸村は入道して好白と号します。父・昌幸はすでに前年病死しています。
慶長19年(1614年)
10月1日 徳川家康が大坂追討を下令すると、豊臣家は諸国の浪人を集める策を採り、幸村にも密使を派遣して参戦を促します。
10月9日 豊臣の密命を受けた幸村は九度山を脱出、嫡子大助とともに大坂城に立て篭もる一方、信濃の真田の旧臣にも檄をとばします。
12月4日 東軍は幸村が玉造口に築いた出城の真田丸を攻めますが、幸村は鉄砲隊を駆使した巧妙な采配によってこれを退けます。
12月20日 大坂方と東軍の間に和議が成立して大坂冬の陣は終結、幸村父子は内に留まります。

By: Ichiro Maruta
慶長20年(1615年)
2月 徳川方は大坂城の備えを崩すため、真っ先に真田丸を破却すると共に、叔父の真田信伊を使者として幸村の寝返りを促します。 しかし、幸村は恩賞としての十万石の所領、信州一国の大名という甘言にも耳を貸さず、これをはねのけます。
4月6日 徳川家康が再び大坂攻めを断行すると、幸村は決死の覚悟で大坂城に籠城します。
5月6日 大坂夏の陣の転換点となる道明寺の戦いが起きます。 この戦いでは、濃霧のために真田隊の戦場到着が遅れ、後藤又兵衛、薄田隼人正ら大坂方の名だたる将が討たれるという事態になります。
しかし、幸村は鉄砲隊を巧みに操って追撃して来る伊達政宗の先鋒を後退させ、豊臣方の撤退を成功させるという功を立てます。
5月7日 損耗が激しい大坂方が形勢を挽回するには大将豊臣秀頼の出陣しかないと考える幸村は、大助を大坂城に人質として送って秀頼の出馬を乞います。しかしそれは果たせず、死を覚悟の最後の作戦を立案します。
家康本陣の右翼に真田隊、左翼に毛利隊勝永を配し、銃撃と突撃をくり返して敵本陣が孤立した隙に、明石全登隊が横合いから急襲するというこの作戦は、功を急ぐ毛利隊の発砲によって破綻し、幸村は正面突破で家康の首を狙うという強襲を行います。
この結果、家康の本陣深くまで攻め入ったものの、最後には数に勝る徳川勢の反撃を受け、四天王寺近くの安居神社まで撤退したところで、越前松平家の鉄砲組西尾宗次に首級を授けることとなりました
真田幸村の年表
>> ホーム(眞田丸) ::: 真田一族 | 眞田丸とは | 六文銭 | リンク│参考文献 | サイトマップ
真田幸村の簡易年表です。
| 永禄十年 | 1567 | 誕生。父昌幸、母山之手殿。武藤弁丸。 | 1歳 | ・ |
| 天正二年 | 1574 | 祖父幸隆死去。 | 8歳 | ・ |
| 天正三年 | 1575 | 昌幸、真田家を継ぐ。真田弁丸。 | 9歳 | 長篠の戦い |
| 天正十年 | 1582 | 真田家の主家、武田氏滅ぶ。 | 16歳 | 本能寺の変 |
| 天正十三年 | 1585 | 幸村、上杉景勝の人質となる。 | 19歳 | 第一次上田城の戦い |
| 天正十四年 | 1586 | 幸村、豊臣秀吉の人質となる。 | 20歳 | ・ |
| 天正十八年 | 1590 | 北条攻め。幸村、初陣か? | 24歳 | 北条氏滅亡 |
| 文禄三年 | 1594 | 幸村、従五位下左衛門佐に任ぜられる。豊臣の姓を承る。豊臣信繁。この頃大谷刑部の娘と結婚? | 28歳 | ・ |
| 慶長三年 | 1598 | 幸村、このころ伏見城にて豊臣家に仕える。 | 32歳 | 豊臣秀吉死去 |
| 慶長五年 | 1600 | 兄の信幸は徳川方へ、幸村は父の昌幸と共に石田方へつく(犬伏の別れ)。 昌幸・幸村、上田城で徳川秀忠軍を破る(第二次上田城の戦い)。 12月頃、幸村、昌幸と共に、高野山九度山村へ蟄居。この頃長男大助生まれる(翌年、翌翌年か)。 | 34歳 | 関ヶ原の戦い |
| 慶長十四年 | 1609 | 弟信勝逐電もしくは斬殺される。 | 43歳 | ・ |
| 慶長十六年 | 1611 | 昌幸死去。 | 45歳 | 二条城の会見 |
| 慶長十七年 | 1612 | 幸村、好白と号す。次男大八生まれる。 | 46歳 | ・ |
| 慶長十八年 | 1613 | 昌幸の妻、山之手殿死去。 | 47歳 | ・ |
| 慶長十九年 | 1614 | 幸村、豊臣家の誘いにより紀州九度山の蟄居先を脱出し、10月大坂城へ入城。大坂冬の陣がはじまる。 12月4日、幸村、大坂城の出城(真田丸)で徳川軍を破る。 豊臣家と徳川家の和平なる。 | 48歳 | 大坂冬の陣 |
| 慶長二十年 | 1615 | 豊臣家と徳川家、再び開戦。5月6日、幸村、誉田の戦いで徳川方と戦い、撤退す。 5月7日、天王寺表の戦い。家康本陣を蹴散らすも奮闘虚しく戦死。 | 49歳 | 大坂夏の陣 |
↧
白鵬長男初土俵
↧
真田一族の史跡
◆真田一族関係史跡一覧◆
| ●秋田県 | |||
| 妙慶寺 | 幸村の五女・御田姫と弟・幸信の墓所 | 岩城町亀田 | |
| ●宮城県 | |||
| 当信寺 | 幸村の三女・阿梅、次男・大八の墓所 | 白石市白石本町 | |
| 白石・田村家墓地の幸村の墓 | 幸村の六女・阿葡萄建立の幸村の墓 | 白石市蔵本勝坂 | |
| ●栃木県 | |||
| 犬伏宿 | 石田三成の密書を父子が密談 | 佐野市犬伏新町 | |
| ●群馬県 | |||
| 天桂寺 | 沼田藩主真田信吉の菩提寺 | 沼田市東原新町 | |
| 正覚寺 | 信之の正室・小松姫の墓所 | 沼田市鍛冶町 | |
| 三光院 | 信利寄進の石灯籠 | 沼田市柳町 | |
| 沼田城 | 昌幸攻略の城 | 沼田市倉内 | |
| 岳山城跡 | 岩櫃城と対立した上杉方の城 | 中之条町五反田 | |
| 林昌寺 | 矢沢頼綱開基の寺 | 中之条町中之条 | |
| 横尾の水牢 | 沼田真田藩の圧政の遺構 | 中之条町横尾 | |
| 中之条町の天王石 | 中之条町の町割りの記念石 | 中之条町中之条 | |
| 鹿沢温泉 | 真田氏の先祖伝説のある温泉 | 嬬恋村 | |
| 顕徳寺 | 武田勝頼を迎えるための居館を移築 | 吾妻町 | |
| 岩櫃城 | 幸隆が落城させた西上州の拠点 | 吾妻町原 | |
| 名胡桃城 | 小田原征伐の口実にされた城 | 月夜野町 | |
| 茂左衛門地蔵 | 沼田藩の圧政を直訴した茂左衛門を弔う | ||
| 尻高城跡 | 昌幸が攻め落とす | 高山村尻高字小屋 | |
| 白井城跡 | 幸隆が攻略した城 | 子持村白井 | |
| ●埼玉県 | |||
| 勝願寺 | 信之正室・小松殿と三男・信重の墓所 | 鴻巣市本町 | |
| ●東京都 | |||
| 青山霊園 | 幸貫の墓 | 港区南青山 | |
| 広徳寺 | 小野お通の墓所 | 練馬区桜台 | |
| 曹渓寺 | 信吉正室・松仙院の墓と信之の供養塔 | 港区南麻布 | |
| 大安寺 | 幸吉の菩提寺 | 港区西麻布 | |
| 海福寺 | 信親家の菩提寺 | 目黒区下目黒 | |
| 松泉寺 | 信勝家の菩提寺 | 渋谷区恵比寿南 | |
| 瑞輪寺 | 信勝家の菩提寺 | 台東区谷中 | |
| ●神奈川県 | |||
| 盛徳寺 | 幸道・幸民の墓所 | 伊勢原市上糠屋 | |
| ●長野県 | |||
| ◎松代 | 開善寺 | 信之が白鳥神社の別当寺にした寺院 | 長野市松代町西条 |
| 海津城(松代城) | 真田家十万石の居城 | 長野市松代町松代殿町 | |
| 川中島古戦場 (八幡原古戦場) | 信玄VS謙信の古戦場 | ||
| 寒松山大林寺 | 昌幸正室・山手殿 | 長野市松代町松代石切 | |
| 皓月山大英寺 | 信之正室・小松殿の菩提寺 | 長野市松代町松代表柴町 | |
| 妻女山 | 上杉謙信が第四回目の川中島戦に本陣を敷いた山 | 長野市松代町清野 | |
| 真田山大鋒寺 | 信之が葬られている寺院 | 長野市松代町柴 | |
| 真田山長国寺 | 松代真田藩主代々の菩提寺 | 長野市松代町松代田町 | |
| 真田邸 | 真田藩第九代藩主幸教の母の隠居所 | 長野市松代町松代殿町 | |
| 西楽寺 | 信重の御霊屋 | 長野市松代町西条 | |
| 文武学校 | 真田藩士の鍛錬場 | 長野市松代町松代殿町 | |
| 松代町の鐘楼 | 旧松代藩の鐘楼 | 長野市松代町松代 | |
| 松代・白鳥神社 | 信之建立の真田家の守護神社 | 長野市松代町西条狼煙山 | |
| ◎上田 | 安楽寺 | 信之が寺領を寄進 | 上田市別所温泉 |
| 上田城跡 | 昌幸が築城し徳川を二度撃退した城 | 上田市上田 | |
| 上田原古戦場跡 | 信玄が村上軍に大敗した古戦場 | 上田市大字上田原 | |
| 米山城跡 | 戸石崩れ(落城)の際の村上吉清の城 | 上田市上野字伊勢山 | |
| 幸村の隠し湯「石湯」 | 真田氏も利用した古湯 | 上田市別所温泉 | |
| 真田幸村の馬上像 | 上田城時代の若武者像 | 上田駅駅前広場 | |
| 松翁山芳泉寺 | 小松殿の宝篋印塔など | 上田市常磐城 | |
| 信濃国分寺跡 | 昌幸徳川方使者との会見場所 | 上田市大字国分 | |
| 天照山大輪寺 | 昌幸再建の寺 | 上田市中央北 | |
| 戸石城跡 | 幸隆、信玄が奪還した城 | 上田市上野字伊勢山 | |
| 矢沢城跡 | 神川左岸を守る城 | 上田市殿上字矢沢 | |
| ◎真田町 | 安智羅宮 | 幸隆、もしくは幸村といわれる神将坐像 | 真田町角間 |
| 角間温泉 | 真田氏隠し湯の一つ | 真田町角間 | |
| 角間渓谷 | 真田忍者修業の場 | 真田町角間 | |
| 真田山長国寺 | 幸隆の妻と昌幸の墓所 | 真田町真田 | |
| 真田氏記念公園 | 真田氏発祥の地 | 真田町本原字下原 | |
| 真田氏館跡 | 信綱の居館 | 真田町長字真田 | |
| 大柏山信綱寺 | 中世真田氏ゆかりの地に建つ寺 | ||
| 日向畑遺跡 | 幸隆以前の真田氏墳墓とされる遺跡 | 真田町角間 | |
| 松尾古城跡 | 真田本城の背後を守る城 | 真田町長字横沢 | |
| 山家神社 | 延喜式に名をみせる真田氏の産土神 | 真田町真田 | |
| ◎丸子町 | 尾野山城 | 上田合戦での千曲川南岸の拠点 | 丸子町生田 |
| 丸子城跡 | 徳川敗退の真田の属城 | 丸子町腰越 | |
| ●福井県 | 安穏寺 | 昌輝の子孫の菩提寺 | 福井市つくも |
| 真田幸村の首塚(真田地蔵) | 幸村を討取った西尾家菩提寺の首塚 | 福井市立郷土歴史博物館 | |
| ●静岡県 | |||
| 花沢城 | 昌幸武勲の城 | 焼津市高崎城山 | |
| ●愛知県 | |||
| 長篠古戦場 | 信綱、昌輝兄弟が戦死 | 鳳来町長篠 | |
| ●京都府 | |||
| 木幡伏見城 | 真田氏が築城に加わった秀吉の居城 | 伏見区桃山町 | |
| 大珠院 | 幸村と正室・竹林院の墓所 | 右京区竜安寺内 | |
| ●大阪府 | 円珠庵(鎌八幡) | 幸村戦勝祈願の神木 | 大阪市天王寺区空清町 |
| 大阪城 | 豊臣家の居城、大坂の陣の舞台 | 大阪市東区大阪城 | |
| 宰相山公園 | 幸村の銅像 | 大阪市天王寺区玉造本町 | |
| 真田丸出城跡(堰月城跡) | 幸村が築いた出城 | 大阪市天王寺区餌差町 | |
| 三光神社・幸村の抜け穴 | 幸村が大坂城との連絡に造ったという洞穴 | 大阪市天王寺区造本町 | |
| 志紀長吉神社 | 幸村戦勝祈願の神社 | 大阪市平野区長吉長原 | |
| 全興時 | 地雷で吹き飛んだ地蔵の首が安置された寺 | 大阪市平野区平野東 | |
| 樋之尻口地蔵 | 幸村が地雷を仕掛けた地蔵堂 | 大阪市平野区平野東 | |
| 安居神社 | 「真田幸村戦死跡」の碑 | 大阪市天王寺区逢坂上之町 | |
| ●和歌山県 | |||
| 高野山・蓮華定院 | 昌幸・幸村父子が配流後身を寄せた寺院 | 高野町 | |
| 善名称院・真田庵 | 昌幸・幸村父子九度山配流の居館 | 九度山町 | |
| ●岡山県 | |||
| 由加山蓮台寺 | 幸村の頌徳碑 | 倉敷市児島由加 | |
| ●香川県 | |||
| 石田・真田家墓地 | 幸村四男・之親の子孫の墓 | 寒川町石田 | |
| ●佐賀県 | |||
| 名護屋城の真田陣跡 | 朝鮮の役での真田父子陣所跡 | 鎮西町名護屋 | |
↧