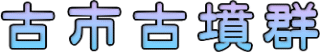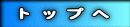ボウリング豆知識
考文献:財団法人全日本ボウリング協会 ボウリング規定集 第7版
【ボール編】
![]()
ボウリングボールは、どんな材質?
最近の主流は「プラスチック」と「ウレタン」に大別されます。 ウレタンボールの方が「曲がる」「弾く」ボールです。金属製のボールは使用できません。
ボールに穴はいくつ開けていいの?
6個所まで開けてもいいことになっています。 通常は、指を入れる穴を3個所・バランスホール(ボールの重心に対して上下左右のバランスをとるための穴)が必要な場合は1個所開けます。
【ピン編】
![]()
ボウリングのピンは、どんな材質?
単一、または張り合わせの"楓(かえで)"で出来ています。
ボールがピンに当たったときの音は?
ピンは、ボールが当たったとき甲高い音を出すために、中心付近に敢えて空洞を作っています。 ピン同士でぶつけあうと、「コンコンッ」と気持ちの良い音がします。 せっかくストライクを出したのに、ゴトゴト・ガタガタ・・・といった音だったら、スカッとしませんからね(^^)
なぜピンは簡単に倒れないの
ピンの重心位置(上下・前後・左右の重さの中心)は、底面から計って約15cmのところにあります。 上の図で言えば、ピンの一番太いところに重心があることになります。 大ざっぱに言うとピンの重量のほとんどが底面に近いところに集まっているので、 ちょっとボールがかすったくらいではなかなか倒れてくれないんですね(:_;)
ピンの寿命は?
ボウリング場によって、ピンの交換周期は様々です。 公認試合には、300ゲーム使用以内の物でなければならないという規則があるので、半年に一度・半分ずつ交換しているというのが一般的のようです。
ピンの並びは?
![]()
- 左の図は、ピンの並びを示しています。図の一番下がレーンの手前側です。 先頭のピンを1番ピンとして、図に示す順番で各ピンに番号がついています。 例えば10ピンといったら10番ピンのことですからいちばん右奥(図でいうと右上)のピンのことを差します。
【スコア編】
ピンを倒した本数分だけの点数で競うのであれば点数計算も楽なのですが、ストライクやスペアには、ボーナスポイントがあります。 このボーナスポイントがボウリングを面白くさせる反面、点数計算を判りづらいものにしているようです。 そこで、ボウリングを面白くさせるためにも点数の計算・スコアの付け方を覚えてみて下さい。
ストライク
![]()
各フレームの第1投目で10本のピン全部を倒すとストライクとなります。このとき、ストライクの得点は10点、 ボーナス得点として次の2投分の得点を加算できます。
上の図を説明すると、(赤字はボーナス得点)
1フレーム:ストライクの10点+2フレームの10点+3フレーム1投目の9点=29点
2フレーム:ストライクの10点+3フレームの1投目の9点+3フレームの2投目の1点+29点=49点
スペア
![]()
各フレームの第1投目で残ったピンを、第2投目で全部倒すとスペアとなります。このとき、スペアの得点10点、 ボーナス得点として次の1投分の得点を加算できます。
上の図を説明すると、(赤字はボーナス得点)
1フレーム:スペアの10点+2フレームの1投目の9点=19点
2フレーム:スペアの10点+3フレームの1投目の7点+19点=36点
ガター
![]()
各フレームの第1投目がガター(左右の溝)に落ちてしまったときにガターとなり「G」のマークが付きます。このとき、得点は0点となります。
上の図を説明すると、(赤字は、スペアのボーナス得点)
1フレーム:ガターの0点+9点=9点
2フレーム:スペアの10点+3フレームの1投目の0点+9点=19点
3フレーム:ガターの0点+7点+19点=26点
ファール
![]()
ボールが手から離れてからつま先などの身体の一部がファールラインを越えたときにファールとなり「F」のマークが付きます。 このとき、得点は0点となりピンは全部立て直されます。 上の図を説明すると、(赤字はスペアのボーナス得点)
1フレーム:ファールの0点+9点=9点
2フレーム:スペアの10点+3フレームの1投目の0点+9点=19点
3フレーム:ファールの0点+7点+19点=26点
ここで気づいた方もいると思いますが、ガターとファールは、同じ扱いになってしまうんです。 特にスペアの後は、どちらもボーナス得点が付かないので大変にもったいないですね。 またファールラインは、ラインの延長上にある壁や柱にも適用されるため、 ボールが手から離れてからファールラインよりもピン側の壁や柱に身体の一部が触れただけでもファールになってしまいます。 逆を言えば、ボールが手から離れていなければ身体の一部がファールラインを越えてもファールにはなりません。
ミス
![]()
各フレームの第1投目で残ったピンを、第2投目で1本も倒せなかったときにミスとなり「-」のマークが付きます。このとき、得点は0点となります。 上の図を説明すると、(赤字は、ストライクのボーナス得点)
1フレーム:7点+ミスの0点=7点
2フレーム:ストライクの10点+3フレームの1投目の8点+3フレームの2投目の0点+7点=25点
3フレーム:8点+0点+25点=33点
このミスは、第2投目のときだけに付くマークです。 2投目にガターとなってしまった場合もミスとなりますが、2投目にファールをしてしまった場合は「F」のマークが付きます。
スプリット
![]()
各フレームの第1投目でヘッドピン(1番ピン)が倒れていて、 2本以上残ったピンが次の条件を満たしているときにスプリットとなります。
・残っているピンの中間のピンが少なくとも1本倒れているとき
(例えば7・9あるいは3・10)
・残っているピンのすぐ前のピンが少なくとも1本倒れているとき
(例えば2・3あるいは5・6)
このとき、1投目で倒れたピンの数字を丸で囲みます。2投目で残ったピンを全部倒すとスペア、1本も倒せないとミスとなります。 また、1投目でヘッドピンが倒せなかった場合は、いくら残ったピンが離れていてもスプリットにはなりません(例えば1・7・9)。 ボウリングは、まずヘッドピンを倒すことが第一条件というボウリング特有のルールの一つなんですね(^^) 最後に、点数計算の練習もかねて珍しいスコアを紹介します。是非、自分で計算してみて下さい。
パーフエクト
![]()
1ゲーム中でストライクを12回連続して出した場合にパーフェクトとなります。 ストライクの計算方法を繰返して行くと、総得点が300点になります。
ダッチマン
![]()
ストライクとスペアを交互に続けた場合、ダッチマンとなります。 これは、ストライクが先でもスペアが先でもよく、総得点は同じ200点となります。
ここに掲載の画像ファイルを含めた文章はyasshiさんの『ボウリング人生バカ一代』より一部変更の上転載させて頂いてます。

























 口永良部島の噴火警戒レベル|気象庁
口永良部島の噴火警戒レベル|気象庁